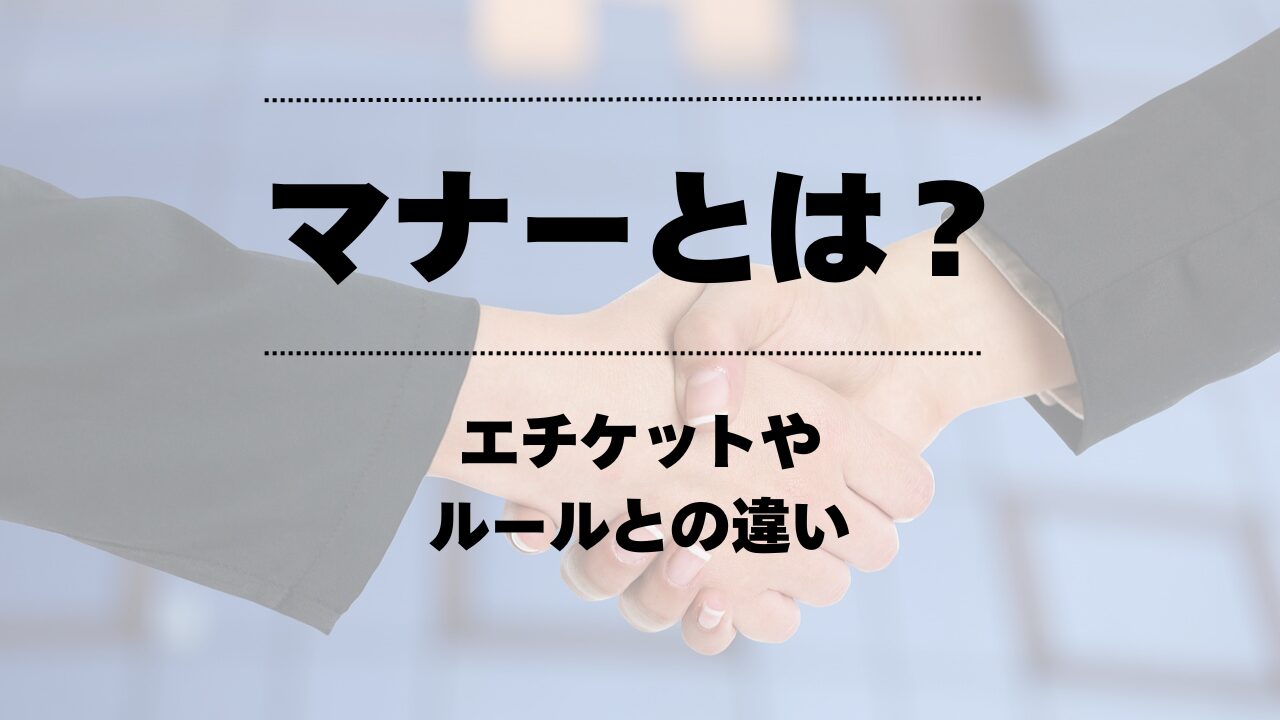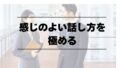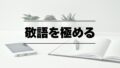日本語の「礼儀作法」と言えば、マナーやエチケットなどのカタカタ語が思い浮かびます。マナーやエチケットの関連語として、ルール、モラル、プロトコールなどがありますが、それぞれどんな違いがあるのでしょうか?
マナーの定義をはじめ、意味が似ているカタカナ語との違い、マナーの特徴についてわかりやすく解説いたします。
マナーとは?

では、はじめに「マナー」の意味から詳しく説明いたします。
マナーの語源
ラテン語の「manuarius」がマナーの語源とされていますが、「手の扱い方」「人の手によった」の意味があります。
マナーの定義
マナーは英語で「manner」と記します。「manner」を英和辞典で調べると、次のような定義が書いてあります。日本語の「マナー」と言えば、複数形で「manners」と綴るのが普通で、次の3番の意味を表します。
| manner [名詞] | ⒈ 方法、やり方 ⒉ 立居振舞、態度 ⒊ (複数形で) 礼儀、行儀作法 ⒋ (複数形で) 慣習、風俗 ⒌ 作風、様式 ⒍ タイプ、種類 |
マナーの真の意味
人間関係の中で求められている行儀/作法で、場面に応じて当然行うべきだと考えられていることです。社会や集団の中で快適に生きるためにマナーは必要であり、他の人が見ているかどうかに関わらず、守った方がいい価値観を示しています。単に形だけでなく、心も含めて表すのがマナーで、他の人たちの立場を考慮する「思いやりの心」が重要視されます。
エチケット、モラルなどの表現はどんな意味?
マナーに似たカタカナ言葉はいくつかあります。エチケット、モラル、ルール、プロトコールなど、誰しも聞いたことがある表現ですが、それぞれの意味の違いはわかりますか?
エチケット

マナーとエチケットは混同して使われるケースが多いですが、明確に定義が違っています。
「etiquette」の語源は古フランス語の「estiquer(貼りつける)」ですが、宮廷に入る時に貼りつけられた「荷札」「訪問者が取るべき行動を記した札」の意から、15世紀頃のフランスにおいて「宮中での礼法」を表すようになったと伝えられています。その後19世紀末にブルジョア社交界の礼儀作法が、現在のエチケットの基盤になりました。
| エチケット | 主観的 | 対個人で相手に不快感を与えないための振る舞い [例] ・くしゃみや咳をする時は手やハンカチで口を押さえる ・食事中に音を立てない |
| マナー | 客観的 | 社会や集団内で皆が快適でいるための振る舞い |
エチケットは目の前にいる相手、マナーは社会や集団の不特定多数の人に対して「思いやる心」を表しています。
モラル

「moral」は個人的な価値観や良心に基づく善悪の判断基準を意味します。語源はラテン語で、「moris(風習)」や「mos(個人の気質)」とされています。モラルは「倫理観/道徳観」と日本語に翻訳されるのが普通です。マナーやエチケットと違って、モラルは振る舞いではなく、気持ちのうえでの善悪の判断を指します。倫理や道徳に反した行動は非難の対象となりますので、注意が必要です。
| モラル | 主観的 | 個人的な価値観や良心に基づく善悪の判断基準 |
| マナー | 客観的 | 社会や集団内で皆が快適でいるための振る舞い |
ルール

社会の中で人が守るべき明文化された規則が「rule」です。語源はラテン語の「regula」で真っすぐな棒を表しています。法律や条例、企業の就業規則、交通ルールなど、社会にはいろいろなルールが存在します。
| ルール | 客観的 | 社会の中で秩序を守るための規則 ・明文化されている ・罰則がある |
| マナー | 客観的 | 社会や集団内で皆が快適でいるための振る舞い |
プロトコール

英語の「protocol」は日本語で国際儀礼と訳されます。外務省によれば、プロトコールは「国家間の儀礼上のルールであり、外交を推進するための潤滑油」と定義されています。
国旗の並び順、席次、服装、招待状、敬称などに関する世界基準の国際マナーがプロトコールなのです。
マナーの特徴

次は、マナーの特徴について2点ご紹介いたします。
マナーは臨機応変に用いる
知り合いに朝出会えば「おはようございます」とあいさつするのが常識です。もし出会った場所が混雑した電車やエレベーターなら、他の人たちに迷惑がかからないよう、あえてあいさつ言葉を言わずに会釈で代用します。このようにマナーの発想では、ルールやエチケットなどを理解したうえで、TPOに合わせた臨機応変な対応を行います。
マナーは変化する
国/地域/社会/時代/文化/民族/宗教などによってマナーは異なります。同じ行為でも国によってマナーにかなっていることもあるし、マナー違反になる場合もあります。また時代の流れに応じてマナーが変化していくのも、特徴の一つです。
| 具体例 | |
|---|---|
| 国/地域で異なる | ・日本: 椀や皿を手で持ち、口元に近づけて食べる ・他国: 椀や皿を持ち上げず、テーブルに置いたまま食べる |
| 時代により変化する | ・新型コロナの影響により「オンライン会議のマナー」が新設される |
まとめ
社会には立場や価値観の違う人たちが共存しています。社会生活を快適に過ごすために、マナー/エチケット/モラル/ルールなどが必要とされます。国際化が広がる現代ではプロトコールも知っておいた方がいいでしょう。表現する形は違っていても、「相手の立場で考える思いやりの心」が必ずベースになっています。主観的に捉えるエチケットやモラル、客観的な規則であるルールをすべて内包しているのがマナーです。国際関係に特化したプロトコールもマナーの一部と言えます。
社会や集団の中で人間関係や信頼関係を安定して築いていくには、ぜひマナーを心得ておきましょう。