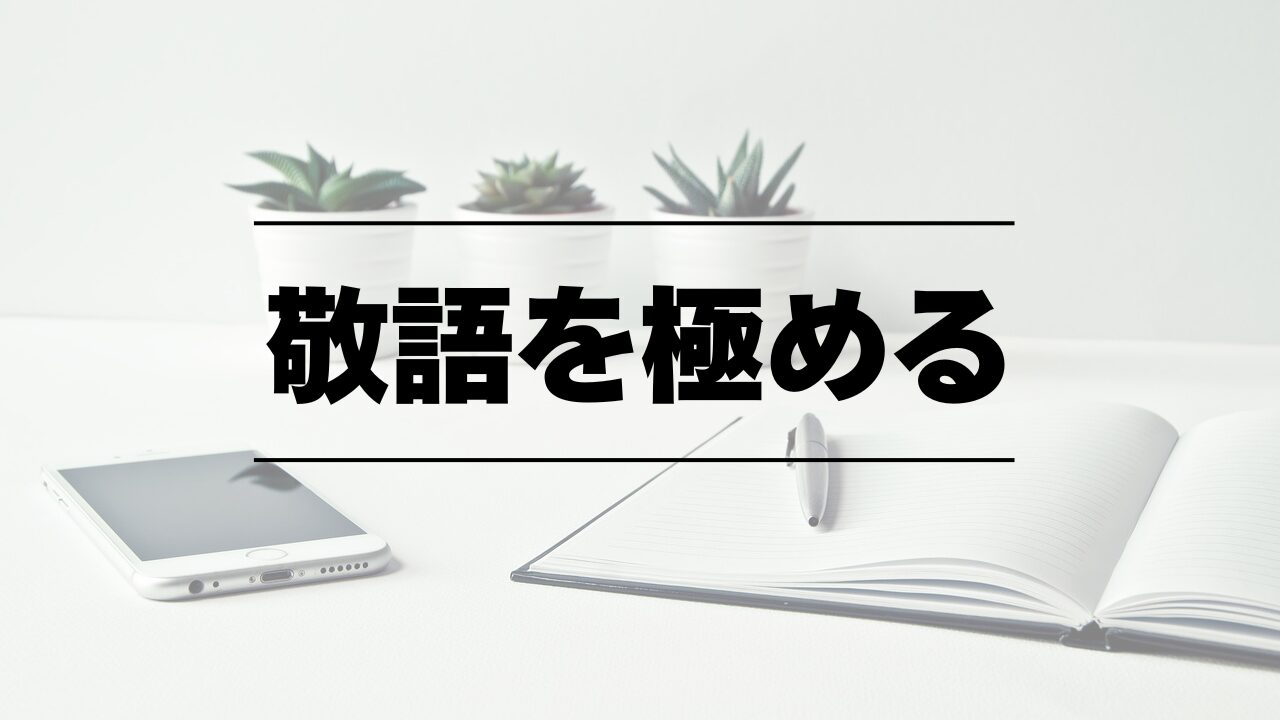「敬語」と聞くと堅苦しいイメージを抱いて、敬語に対して苦手意識を持っている人が多いと言われます。学生のうちはタメ口が許されても、社会人になったら敬語を使うのが世間の常識です。就職活動中の人や新入社員の場合、ビジネスマナーの一環として改めて敬語を覚える必要に迫られます。
国語の時間に誰もが一度は敬語を学んでいるはずなのに、ビジネスの場や日常生活で間違った敬語を使っているケースが頻繁に見受けられます。
自信を持って敬語を使いこなせるよう、敬語の定義、敬語の種類、敬語で注意すべきポイントについてわかりやすく解説いたします。
敬語とは?

敬語は「敬う(うやまう)語」と書きますが、どのような言葉なのでしょうか?
まず敬語の定義と必要性についてご紹介します。
敬語の定義
敬語とは「人を敬う言葉」の意で、別名「調和語」と呼ばれています。人間関係の中でさまざま生じる差や違いを調和してくれる便利な表現が、敬語なのです。
敬語はなぜ必要?
人間関係を考えるとき、年齢・性別・地位などの面で違いがあることを念頭に置かなくてはいけません。敬語は、人との違いを調和して対等にコミュニケーションをするための有効なツールです。
敬語を適切に使いこなせば、相手のことを尊重しながら同じ立場になってコミュニケーションができます。
敬語の種類
敬語は大別して、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類あります。
尊敬語
尊敬語は、相手や相手側のことに対して尊敬の気持ちを表す言葉です。イメージとしては、相手に「尊敬」の座布団を敷いて、直接的に相手の位置を高くします。
謙譲語
自分や自分側のことをへり下る言葉が謙譲語です。「謙譲」の階段を自分が一段下がることで、間接的に相手を高い位置にします。
丁寧語
言葉自体を丁寧にするのが丁寧語の役割です。ことばにラッピングをしてきれいに見せるイメージです。
【敬語の種類まとめ】
| 敬語の種類 | 対象 | 定義 | イメージ |
|---|---|---|---|
| 尊敬語 | 相手 | 相手を高める | 相手に座布団を敷く |
| 謙譲語 | 自分 | 自分をへり下る | 自分が階段を一段下がる |
| 丁寧語 | 言葉 | 言葉をきれいにする | 言葉にラッピングする |
敬語の基本パターン
尊敬語、謙譲語、丁寧語にはそれぞれ基本パターンがありますので、ぜひ覚えておきましょう。
尊敬語のパターン
| 品詞 | 基本パターン | 例 |
|---|---|---|
| 名詞 | 1 前置きA:「お/ご」 + 名詞 前置きB: 尊敬の意の漢字 + 名詞 2 後置き:名詞 + 敬称 (「様」、役職名など) | 1 A: お考え、ご意見 B: 貴社、御社 2 〇〇先生、〇〇部長 |
| 形容詞/ 形容動詞 | 前置き:「お」 + 形容詞/形容動詞 | お美しい おきれいだ |
| 動詞 | 1 〜れる/られる 2 お/ご〜になる 3 (お/ご)〜なさる [尊敬の程度は1から3の順に重くなる] | 1 待たれる 2 お待ちになる 3 お待ちなさる |
| 相手が〜してくれる (尊敬の依頼形) | 1 〜(し)てくださる 2 お/ご〜(なって)くださる [尊敬の程度は1から2の順に重くなる] | 1 待ってくださる 2 お待ちくださる |
謙譲語のパターン
| 品詞 | 基本パターン | 例 |
|---|---|---|
| 名詞 | 1 前置きA: 「お/ご」 + 名詞 (自分の行為が相手に及ぶ場合に限る) 前置きB: 謙譲の意の漢字 + 名詞 2 後置き: 名詞 + 「ども」 | 1 A: お電話、お手紙、ご説明、ご案内 B: 弊社、粗品 2 私ども |
| 動詞 | 1 〜(さ)せていただく 2 お/ご〜する/いたす (申す/申し上げる) [謙譲の程度は1から2の順に重くなる] | 1 待たせていただく 2 お待ちする/いたす(申す/申し上げる) |
| 相手に〜してもらう (謙譲の依頼形) | 1 〜(し)ていただく 2 お/ご〜いただく 3 お/ご〜願う [謙譲の程度は1から3の順に重くなる] | 1 待っていただく 2 お待ちいただく 3 お待ち願う |
丁寧語のパターン
| 品詞 | 基本パターン | 例 |
|---|---|---|
| 名詞 | 前置き:「お/ご」 + 名詞 | お味噌汁、ご飯 |
| 文体 | 1 〜だ/である。 (常体) 2 〜です/ます。 (敬体) 3 〜ございます。(最敬体) | 1 私は〇〇だ/である。 2 私は〇〇です。 3 私は〇〇でございます。 |
敬語の特別表現
敬語にはそれぞれ基本パターンがあることがわかりましたが、特に動詞は、例外的な特別表現が存在します。基本パターンとともに例外の敬語もしっかりマスターしておきましょう。
| 動詞 | 謙譲語 |
|---|---|
| 読む | 拝読する/いたす |
| 借りる | 拝借する/いたす |
| 聞く | 伺う、承る、拝聴する/いたす |
| 聞かせる | お耳に入れる |
| 見せる | お目にかける |
| 会う | お目にかかる |
| 動詞 | 尊敬語 | 謙譲語 |
|---|---|---|
| いる | いらっしゃる | おる |
| する | なさる | いたす |
| 言う | おっしゃる | 申す、申し上げる |
| 見る | ご覧になる | 拝見する/いたす |
| 行く | いらっしゃる | 参る、伺う |
| 来る | いらっしゃる、お越しになる、 おいでになる、おみえになる | 参る、伺う |
| 食べる | 召し上がる | いただく、頂戴する/いたす |
| もらう | 「受ける、受け取る」の基本パターン | いただく、頂戴する/いたす |
| 与える | くださる | 差しあげる、あげる |
| 知っている | 知って/ご存じでいらっしゃる | 知っておる、存じあげる |
敬語の注意点
人間関係の調和をうまく図るため、敬語は正しく使うように心がけます。下記のとおり、敬語は間違えやすい点が5つありますが、中でも最初の2つは最も頻発しやすい間違いです。
十分に注意して敬語を用いるようにしましょう。
尊敬語と謙譲語の使い誤り
尊敬語と謙譲語を混同して、間違った敬語を使ってしまうケースはよくありがちです。相手には尊敬語、自分には謙譲語を使うのが大前提です。
敬語の基本パターンと特別表現を区別して、使い誤らないようにしましょう。
【使い誤りの例】
| 誤った表現 | 理由 | 正しい表現 |
|---|---|---|
| 「窓口で伺ってください。」 | 「伺う」は謙譲語 →尊敬語 | 「〜お聞き/お尋ね(になって)ください。」 |
| 「申込書をご持参ください。」 | 「持参」は謙譲語 →尊敬語 | 「〜お持ち(になって)ください。」 「〜お持ちになってお越しください。」 |
| 「ご注意してください。」 | 「ご注意する」は謙譲語 →尊敬語 | 「ご注意(になって)ください。」 |
| 「少々お待ちしていただけますか。」 | 「お待ちする」は謙譲語 →尊敬語または謙譲語の依頼表現が適切 | 「〜お待ち(になって)ください。」 「〜待っていただけますか。」 「〜お待ちいただけますか。」 「〜お待ち願えますか。」 |
二重敬語
尊敬語を重ね過ぎる、謙譲語をダブって使うことは「二重敬語」と呼ばれます。現代の国語では文法上間違いとされるため、過剰な敬語表現にならないように気をつけます。動詞は基本パターンどおり忠実に当てはめるようにして、絶対に変形させたり混合させたりしないよう注意しましょう。
| 誤った表現 | 理由 | 正しい表現 |
|---|---|---|
| 「おっしゃられたとおりです。」 | 「おっしゃる」を「〜れる/られる」に当てはめるのはNG | 「おっしゃったとおりです。」 「言われたとおりです。」 |
| 「お聞きになられましたか。」 | 「お聞きになる」に「〜れる/られる」を付けるのはNG | 「お聞きになりましたか。」 「聞かれましたか。」 |
| 「お召し上がりになりますか。」 | 尊敬語「召し上がる」を基本パターンに入れる必要なし | 「召し上がりましたか。」 「お食べになりましたか。」 |
| 「ご参加されますか。」 | 尊敬語の基本パターンどおりの形になっていない | 「参加なさいますか。」 「ご参加になりますか。」 「参加されますか。」 |
| 「お休みさせていただきます。」 | 謙譲語の基本パターンと違っている | 「お休み(いた)します。」 「休ませていただきます。」 |
ウチとソトの感覚
ソトは尊敬語、ウチには謙譲語を用いるのが原則です。
ウチとソトとの線引きが正しくない場合、間違った敬語を使ってしまう恐れがあります。ウチとソトの線引きをする際の目安は次のとおりです。
| お客様に対して | 自社内の者はすべて「ウチ」と扱う |
| 上司や同僚の家族に対して | 上司や同僚を「ソト」扱いする |
| 他の人に対して | 自分の家族や身内は「ウチ」扱いする |
| 誤った表現 | 正しい表現 |
|---|---|
| (客に) 「うちの加藤部長は外出されています。」 | 「私ども/当社の部長の加藤は外出しております。」 |
| (上司の奥様に) 「加藤はただ今外出しております。」 | 「加藤部長はただ今外出していらっしゃいます。」 |
| (知人に対し) 「おじいちゃんが本日上京されます。」 | 「祖父が本日上京いたします。」 |
敬語をつける対象
敬語のうち、尊敬語と謙譲語は人に対して、丁寧語は言葉に対して使います。今話していることが何を対象にしているか十分に意識して、適切な敬語を使う必要があります。
特に、物や動物などが主語や主体になるときは、尊敬語も謙譲語も使ってはいけません。あくまでも丁寧語をベースに表現しましょう。
| 誤った表現 | 正しい表現 |
|---|---|
| 「専務のお宅には犬が何匹いらっしゃいますか。」 | 「いらっしゃる」は尊敬語 →「〜には犬が何匹いますか。」 ★主語を専務にすれば尊敬語が使える →「専務はお宅で犬を何匹飼っていらっしゃいますか。」 |
| 「鳥にエサをあげました。」 | 「あげる」は謙譲語 →「鳥にエサをやりました/与えました。」 |
敬語を使う程度
敬語を知っているから何でもかんでも使えばいいと言うことではありません。
敬語にもレベルがあり、軽めのものから重めの表現まで程度が違っています。過度に敬語を使い過ぎると慇懃無礼(いんぎんぶれい)と受け取られる可能性があるので、気をつけるべきです。
具体例として、一つの文章の中に同一人物の行為を表す動詞が複数入っている場合、どのように敬語を用いたらよいか解説いたします。尊敬語・謙譲語ともに、下表の①が一番軽めで、数字が大きくなるほど敬語のレベルが高くなります。
敬語に慣れるまでは、最小限の敬語を用いる①から始めるといいでしょう。
【原文が「山田さんが説明するために来た。」の場合】
| 敬語 | 敬語を用いた文章 |
|---|---|
| 尊敬語 | 1 「山田様が説明するために来られました。」 2 「山田様が説明されるために来られました。」 3 「山田様が説明するためにいらっしゃいました。」 4 「山田様がご説明になるためにいらっしゃいました。」 |
| 謙譲語 | 1 「山田が説明するために参りました。」 2 「山田がご説明するために参りました。」 3 「山田がご説明いたすために参りました。」 |
まとめ
敬語は、人間関係の差を埋めてくれる効果的なコミュニケーションツールです。尊敬語、謙譲語、丁寧語の定義をきちんと理解したうえで、基本パターンから例外の特別表現まで覚えておくようにしましょう。間違えやすい注意点として挙げた5つの中でも、特に、尊敬語と謙譲語の使い誤りと二重敬語に気をつけて、ビジネスや日常生活の中で適切な敬語を正しく使えるようになることが必要です。