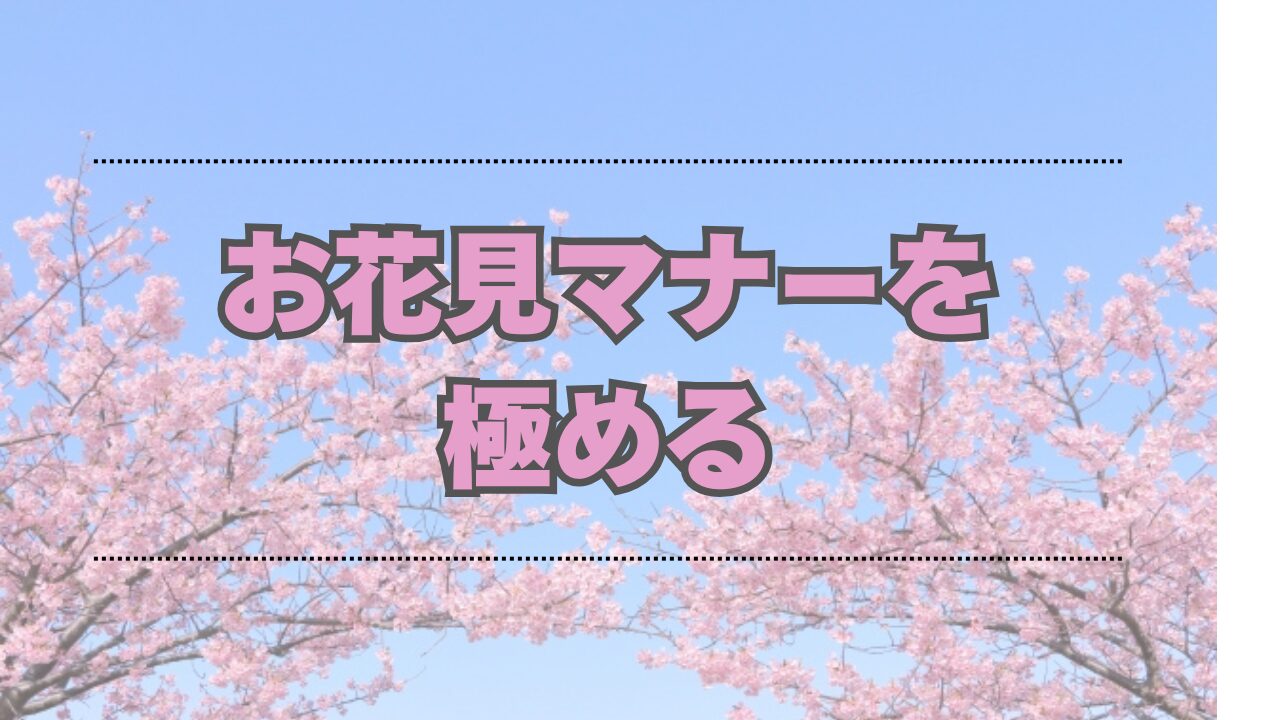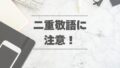日本文化の中で毎年大切な行事として古来より伝わってきたのが「お花見」です。お花見の定義、由来や歴史から、桜の種類やお花見の食べ物、お花見のマナーまで詳しく解説いたします。
お花見とは?

日本の春の主要行事として根付いているお花見ですが、お花見の定義や日本で普及した理由などについて紹介いたします。
「お花見」の定義
「花見」とは、季節の花を鑑賞しに出かける日本独特の風習です。四季がある日本では、時季に応じた花の盛りを見に行き、新しい季節の訪れを喜びます。梅、桃、桜、菜の花、つつじ、藤、紫陽花、牡丹、バラ、ひまわり、コスモス、菊、椿など花の見頃が一年中あり、それぞれの有名なスポットが全国各地に点在し大勢の人が殺到します。
日本の代表的な花である梅は「観梅」「梅見」、菊は「観菊」「菊見」と呼ばれるのが普通ですが、古くから日本で「お花見」と言えば「桜」を観賞してきました。お花見は農民による豊作祈願のための神事としての意味合いもあります。春が来ると田んぼの神様が山から降りてきて桜の木に宿ると信じられていて、桜の咲き具合でその年の米の収穫高を占ってきました。
なお、「お花見」には、「観桜(かんおう)」「桜狩り(さくらがり)」など別の呼称もあります。
「桜」の語源

「桜」の語源は諸説ありますが、一説では「さ」は田んぼの神様、「くら」は神の座る所を意味するとのこと。桜の花が稲の花と見なされて、桜の木に宿った田んぼの神様を春に迎え、酒や料理でもてなして豊作を祈願することが花見の由来であるという説があります。
「お花見」が日本文化に定着した理由
お花見の対象になる「桜」は短期間で開花し満開になり、雨風が強いと一気に散ってしまいます。春の天気は移ろいやすく、桜の見ごろは平均して約2週間程度です。花吹雪で散る桜の美しさと儚さが日本人の無常感に結びついているのが、日本人が特に桜を愛でる大きな理由でしょう。
お花見の歴史
次に日本における「お花見」の歴史や変遷について簡単に紹介いたします。
最初のお花見は桜でなかった?
奈良時代の記録では、貴族が花を愛でる習慣があったそうです。ただし、当時の「花」といえば「桜」でなく「梅」のことを意味していました。『万葉集』で梅を詠んだ歌が約110首あるのに対し、桜の歌は43首でした。その後10世紀はじめの『古今和歌集』では逆転して、梅の歌が18首、桜が70首になりました。この時期から「花」といえば「桜」と考えられ、桜は神木として崇められ、神が宿る桜が信仰されるようになりました。
「桜狩り(さくらがり)」とは?
辞書によれば、桜の花を求めて山野を遊び歩くことが「桜狩り」で、鷹狩りの異名にもされています。「桜狩り」は「お花見」よりも昔から用いられており、平安時代中期の書物「宇津保物語」で使われていました。当時の貴族は、春に「桜狩り」、秋は「紅葉狩り」を行って季節感を味わいました。
そのうち天皇の御所と同様、次第に平安貴族たちも自邸の庭へ桜を植えて、山野へ行かずに自宅で花見をするようになりました。
お花見の起源
お花見の対象が梅から桜へ変わったのは平安時代以降のこと。嵯峨天皇が催した花宴が桜のお花見の起源と考えられています。桜の花を見ながら貴族たちが歌詠みや蹴鞠(けまり)を楽しんだと記録が残っています。はじめは貴族主体のお花見の行事でしたが、次第に武士の世界へ伝わって、かの有名な「醍醐の花見」や「吉野の花見」を催したのは豊臣秀吉でした。
お花見が庶民に定着したのは江戸時代から
江戸時代の寛文年間(1661~1673年)を迎えると庶民の間でもお花見を行う習慣が定着しました。
中でも農民は農作業を始める時期を桜の開花をきっかけにしていたので、神が宿る桜を見ながら宴を行い五穀豊穣を祈ったと言われます。
江戸時代初期はお寺の境内に植えてある桜を見に行くのが常でしたが、徳川吉宗の時代(享保1716~1736年)になると隅田川堤や小金井堤、飛鳥山などに桜の木が数千本も植樹され、庶民の行楽を奨励しました。その結果、桜の木の下でお弁当を食べるお花見文化が庶民にまで一気に浸透しました。
桜の種類
桜は北半球側の温帯地域で見られる植物で、品種によりバラ科もしくはサクラ亜科に分類されます。海外でも桜を見かけることは多いですが、やはり花の美しさにおいては日本の桜が最も有名です。
古くから日本では野生種の「ヤマザクラ」が主流でしたが、江戸時代後期から桜の交配や改良が進んで約300種ほど加わり、今では日本だけで500種類超あると言われています。中でも「ソメイヨシノ」は栽培しやすい利点から、江戸末期~明治にかけて全国各地に普及しました。
では、日本でよく見られる主な桜の種類について下表にまとめます。
【野生種】

日本に自生する桜の野生種は全11種ありますが、一部ご紹介します。
| 特徴 | |
| 山桜(ヤマザクラ) | ・山に自生する桜の総称 ・白~薄ピンク色、一重咲 ・古くから和歌で詠まれ、江戸中期まで桜といえば山桜を指す ・花と葉が同時に出る ・葉は赤/赤紫~褐色 |
| 大島桜(オオシマザクラ) | ・白色、一重咲 ・伊豆大島が発祥の地で、全国へ拡大 ・桜餅用の葉として使われる ・花と葉の香りが特徴的 |
| 江戸彼岸桜(エドヒガンザクラ) | ・白~薄ピンク色、一重咲 ・春の彼岸頃に開花するのに因む ・葉が出るのは花が咲いた後 ・病気に強く寿命が長い(樹齢千年超もある) ・天然記念物指定されることも |
| 霞桜(カスミザクラ) | ・薄ピンク色、一重咲 ・山桜にそっくり ・葉に毛が生えるので別名「毛山桜(ケヤマザクラ)」 ・北寄りで自生 ・4月下旬から5月上旬と開花が遅め |
| 豆桜(マメザクラ) | ・白~薄ピンク色、一重咲 ・他の品種より小ぶりで可愛らしい形状から命名 ・富士山周辺に多く自生 ・「富士桜(フジザクラ)」「箱根桜(ハコネザクラ)」が別名 ・挿木(さしき)でも育てられる |
| 寒緋桜(カンヒザクラ) | ・濃ピンク色、一重咲 ・美しい緋色で、花がベルの形状 ・花首ごと落ちて散る ・沖縄県では桜の開花時期として観測 |
【有名な6品種】

桜の交配種のうち、有名な品種6つをご紹介します。
| 特徴 | |
| 染井吉野(ソメイヨシノ) | ・薄ピンク色、一重咲 ・江戸末期から明治初期に大島桜と江戸彼岸桜を交配して改良 ・染井村(現在の東京都豊島区駒込)の植木屋が発売 ・奈良県の吉野山にちなんで命名 ・現在日本の桜の8割程度 ・気象庁が開花宣言発表の指標とする |
| 枝垂桜(シダレザクラ) | ・枝が細く花の重みで垂れ下がるタイプの桜の総称 ・品種により花色は白~濃ピンク、一重~八重咲 ・京都は平野神社や上賀茂神社など名所が多く、府花に指定 |
| 八重桜(ヤエザクラ) | ・八重咲き桜の総称 ・楊貴妃(ヨウキヒ)、手毬(テマリ)、関山(カンザン)など品種が多い ・花が豪華で盆栽や地植えとしても人気 |
| 河津桜(カワヅザクラ) | ・濃ピンク色、八重咲 ・大島桜と寒緋桜を交配 ・静岡県賀茂郡河津町で発見 ・1月下旬から3月上旬頃に早咲きする八重桜 ・風雨に強い |
| 寒桜(カンザクラ) | ・薄ピンク色、一重咲 ・寒緋桜および、山桜または大島桜との交配 ・早いと1~2月から開花 ・静岡県熱海市で多く見られる、別名は「熱海桜(アタミザクラ)」 |
| 冬桜(フユザクラ) | ・白~薄ピンク色、一重咲 ・山桜と豆桜を交配 ・春秋の年2回咲く ・秋は10~12月に開花、運がいいと紅葉と同時期に咲く ・小さめの花で、「四季桜」「小葉桜(コバザクラ)」とも呼ばれる |
お花見に欠かせない食べ物
お花見に縁の深い食べ物について紹介します。
花見弁当

桜・筍・山菜など、春の旬の食材を用いて作った春らしい色鮮やかな花見用のお弁当を指します。すでに江戸時代には花見弁当が流行していて、当時の料理本に花見弁当の献立が掲載されました。また、日本酒も入れられる花見専用の特別な重箱が使われていた記録が残っています。
桜菓子
お花見や桜にまつわるお菓子と言えば、桜餅と花見団子が有名です。和菓子2種類について下記にまとめます。
桜餅
関東と関西で桜餅のタイプがまったく異なります。機会があれば食べ比べしてみましょう。

| 関東 | ・小麦粉の生地を薄く焼いて、あんこを巻いたクレープ ・別名「長命寺」 ・長命寺門前で発売されたことに由来する ・隅田川沿いの桜の葉を使用 |
| 関西 | ・道明寺粉と呼ばれる餅米を使って、こしあんを包んだ饅頭 ・別名「道明寺」 ・表面のつぶつぶ食感が特徴的 |

花見団子

お花見に欠かせない3色串団子で、各色に意味があります。ピンク色が桜で春の喜びを、冬の名残り雪を白で、地中の新緑をよもぎの緑で表現しています。
桜の塩漬け

| 桜の花 | ・八重桜の塩漬け ・「桜湯」はお茶の代わりにお祝いごと(結婚や結納)で出される (茶を濁すことから、お茶は縁起が悪いとされるため) ・和菓子だけでなく、炊き込み/混ぜご飯、お寿司やお茶漬けにも使用 |
| 桜の葉 | ・主に大島桜が使われる ・桜餅に使用(関東は大きめ、関西は小さめ) ・葉の形状を生かしてデザートやおにぎりなど、春のお料理で幅広く活用 |
お花見のマナー

春の花といえば第一に桜を連想しますが、桜を愛でる行事として現在でも花見は盛んに行われています。環境問題がしきりに叫ばれる昨今、最新版「お花見のマナー」をご紹介します。
場所取りは節度を持って
花見の場所取りをする時は、参加人数に合わせて適度なスペースを確保するように心がけます。自分たちだけのために便宜を図るのはマナー違反です。あくまでも必要最低限のスペースに留めて、周囲に配慮する精神を持ちましょう。他の人たちの場所を横取りするのはNGです。
桜を大切にする
どんなに桜が好きでも、決して枝を折ったり花を摘んだりしてはいけません。植物も命ある生き物です。特に桜は繊細な植物なので大切に扱うようにしましょう。また、桜の木の根元にビニールシート類を敷くと、根に傷がつきやすく呼吸を妨げてしまいます。桜の木から少し距離を離してシートを設置して座るようにしましょう。場所取りの際に桜の木や枝にロープを結んだりテープを貼ったりしないようくれぐれも注意すべきです。木に登ったり枝にぶら下がったりするのは、たとえ子どもであっても厳禁です。
騒がしくしない
お酒に酔った勢いでどんちゃん騒ぎをすると周りの人たちや付近の迷惑になります。内輪が楽しければそれでいいという発想はやめましょう。特に住宅街の近くでは、夜遅い宴会は避けて少し早めに切り上げて帰るようにします。あくまでも桜を見ながら節度を持って楽しむべきです。子どもを連れて行く場合も、騒いだり走り回ったりしないよう保護者が事前に注意してしつけておきます。
ゴミは持ち帰る
ゴミ箱が設置してあっても、皆が無造作に捨てると溢れかえって美観を損ねます。環境保護の対策として、お弁当の容器や空き缶、ペットボトルなど、原則ゴミは自分で持ち帰るようにしましょう。できれば使い捨てではなく、リサイクルできる容器やカトラリーを利用してゴミを出さないのが現代流のマナーです。
トイレを確認しておく
お花見をする場所にはトイレが少ない恐れがあります。現地に着いたら、まずトイレの場所と数を確かめておくのがおすすめです。川沿いや山野で花見をする場合は、トイレを見つけ次第、取りあえず行っておいた方が安心でしょう。
まとめ

桜は日本人の心に通じる魅力的な花です。平安時代から続く「お花見」の文化を、お花見の歴史や桜の語源、桜の種類を理解したうえで、ぜひ五感で味わってみましょう。時期や場所によってさまざまな種類の桜が楽しめるはずです。一人でゆっくり桜を満喫してもいいし、家族や友人と一緒にお花見弁当持参で桜の美しさを共有するのもOKです。ただし、お花見のマナーとして、周囲と環境、そして桜に対する配慮を忘れないことが大切です。