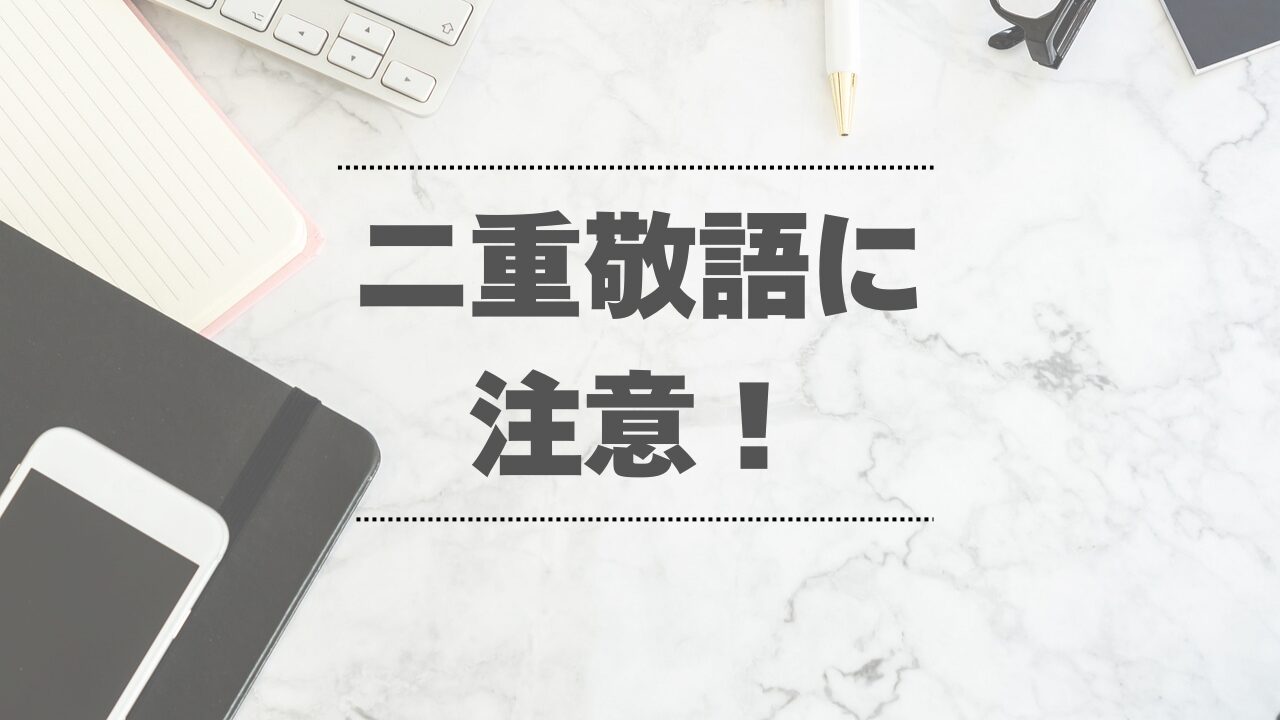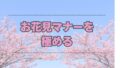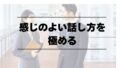敬語に関する間違いのうち、「二重敬語」は頻度の高いミスの上位に挙げられます。よく話題にされる二重敬語ですが、いったいどのような敬語なのでしょうか?
今回は、二重敬語の定義をはじめとして、二重敬語を使わないための対策、典型的な二重敬語の例や注意点などについて詳しく解説いたします。
「二重敬語」とは?

そもそも二重敬語とはどのような言葉を指しているのでしょうか?二重敬語の定義や、二重敬語がNGの理由、二重敬語を使ってしまう要因について取り上げてみます。
二重敬語の定義
「二重敬語」とは、すでに敬語になっている状態の言葉に同種類の敬語をさらに重ねていることで、現代の文法では誤りと見なされます。
なお、文化庁のHPに二重敬語についての記載がありますので、下記に引用いたします。
"一つの語について,同じ種類の敬語を二重に使ったものを「二重敬語」と言います。例えば,「お読みになられる」は,「読む」を「お読みになる」と尊敬語にした上で,更に尊敬語の「……れる」を加えたもので,二重敬語です。「二重敬語」は,一般に適切ではないとされています。ただし,語によっては,習慣として定着しているものもあります。"
▶︎ 文化庁 「第4話 『間違えやすい敬語⑴ 〜尊敬語 VS 謙譲語Ⅰ』理解度チェックの解答」
二重敬語NGの理由
昔は当たり前に使われていた二重敬語。現代では敬語を使い過ぎると、かえって丁寧過ぎてくどくどしく思われたり、慇懃無礼(いんぎんぶれい)と受け取られたりする恐れがあります。文法的に間違いになるだけでなく、二重敬語にすると明らかに文字数が増えるため、口頭でも文面でも伝達効率が悪くなります。
二重敬語を使ってしまう要因
相手を尊敬したり自分をへり下ったりしようと意識しすぎて、尊敬語を重ねて使ったり謙譲語をダブらせたりする「二重敬語」が多くなりがちです。また、敬語に関する知識不足が原因となって、気づかないうちに二重敬語を使ってしまうケースもあります。
二重敬語を使わないための対策
誤って二重敬語を使わないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?下記の3つの対策が考えられますので、すぐに実践してみましょう。
| ⒈ 二重敬語について知る | 二重敬語がどんな言葉か知るようにする |
| ⒉ 敬語を正しく理解する | 敬語について正確に理解できるように努める |
| ⒊ 普段から適切に敬語を用いる | 仕事や日常生活の中で普段から敬語を用いて、使い慣れるようにする |
二重敬語について知る
二重敬語について知識を深めれば、二重敬語を用いるリスクは防ぐことができます。二重敬語を使わないようにする第一歩として、まずは二重敬語がどんな言葉なのかを把握しておきましょう。よく見かける二重敬語の典型例7つを紹介いたします。
二重敬語の典型的な7例
文法の面から、二重敬語は正しい使い方ではありません。敬語表現を重ねて用いないよう日頃から十分に気をつけましょう。特に、動詞を敬語に変換する場合は、忠実に基本パターンへ当てはめる、特殊表現はむやみに変形させないように注意する必要があります。
| 二重敬語の例 | 正しい表現 |
|---|---|
| 社長様 | 社長、社長の〇〇様 |
| お帰りになられる | 帰られる、お帰りになる |
| おっしゃられる | 言われる、おっしゃる |
| ご出席される | 出席される、ご出席になる、(ご)出席なさる |
| お休みさせていただく | 休ませていただく、お休みする/いたす |
| 伺わせていただく | 伺う |
| 拝見させていただく | 拝見する/いたす |
なお、文化庁HPの中で、習慣により定着している二重敬語として下記の例が挙げられています。
【習慣として定着している二重敬語の例】
・(尊敬語) お見えになる
・(謙譲語I)お伺いする,お伺いいたす,お伺い申し上げる
▶︎ ︎文化庁 「第4話 『間違えやすい敬語⑴ 〜尊敬語 VS 謙譲語Ⅰ』理解度チェックの解答」
三重敬語も存在する
一つのことばに敬語を重ねて付けるのが二重敬語ですが、場合により三重敬語も存在します。
例えば、食べるの尊敬語「召し上がる」を尊敬語の基本パターン「お~になる」に入れて、さらに尊敬の助動詞「~れる/られる」に当てはめると、「お召し上がりになられる」という三重敬語になります。
敬語連結と混同しない
敬語連結とは、2つのことばを接続助詞の「て」で連結させて各々を敬語に変換した言葉です。敬語連結すると少し長めの表現になりますが、二重敬語と違って、文法上の問題はありません。
二重敬語と敬語連結はまったく別物なので、混同しないよう注意が必要です。
【敬語連結の例】
| 敬語連結 | |
|---|---|
| 書いている (「書く」尊敬語+「いる」尊敬語) | お書きになっていらっしゃる |
| 書いてくれる (「書く」尊敬語+「くれる」尊敬語) | お書きになってくださる |
| 書いてもらう (「書く」尊敬語+「もらう」謙譲語) | お書きになっていただく |
| 説明してあげる (「説明する」謙譲語+「あげる」謙譲語) | ご説明してさしあげる |
敬語を正しく理解する
よい人間関係を維持するうえで必要不可欠なコミュニケーションツールの一つが敬語です。
敬語は、次表のとおり、尊敬語・謙譲語・丁寧語の3種類に分けられます。
敬語の種類
| 種類 | 対象 | 定義 | イメージ |
|---|---|---|---|
| 尊敬語 | 相手 | 相手を高める | 相手に座布団を敷く |
| 謙譲語 | 自分 | 自分をへり下る | 自分が階段を一段下がる |
| 丁寧語 | ことば | ことばをきれいにする | ことばにラッピングする |
各敬語の定義を正確に理解したうえで、基本パターンと例外の特殊表現をしっかり覚えておきましょう。
尊敬語
尊敬語は、相手に対して尊敬の意味を込める言葉です。名詞、形容詞/形容動詞、動詞に対する尊敬表現があります。
【尊敬語の基本パターン】
| 品詞 | 基本パターン | 具体例 |
|---|---|---|
| 名詞 | ① 前置きA:「お/ご」 + 名詞 前置きB:尊敬の意の漢字 + 名詞 ② 後置き: 名詞 + 敬称 (「様」、役職名など) | ① 前置きA: お考え、ご意見 前置きB: 貴社、御社 ② 〇〇先生、〇〇社長 |
| 形容詞/形容動詞 | 前置き:「お」 + 形容詞/形容動詞 | お美しい、おきれいだ |
| 動詞 | ① ~れる/られる ② お/ご~になる ③ (お/ご)~なさる | ① 待たれる ② お待ちになる ③ お待ちなさる |
| 相手が~してくれる (尊敬の依頼形) | ① ~(し)てくださる ② お/ご~(なって)くださる | ① 待ってくださる ② お待ちくださる |
謙譲語
謙譲語は自分をへり下る表現です。「謙譲」の階段を自分が一段下がる方法で、相手が間接的に高い位置になるようにします。名詞と動詞に対して謙譲語が使えます。
【謙譲語の基本パターン】
| 品詞 | 基本パターン | 具体例 |
|---|---|---|
| 名詞 | ① 前置きA:「お/ご」+ 名詞 (自分の行為が相手に及ぶ場合に限る) 前置きB:謙譲の意の漢字+名詞 ② 後置き:名詞 + 「ども」 | ① 前置きA:お電話、お手紙、ご説明、ご案内 前置きB: 弊社、粗品 ② 私ども |
| 動詞 | ① ~(さ)せていただく ② お/ご~する/いたす(申す/申し上げる) | ① 待たせていただく ② お待ちする/いたす |
| 相手に~してもらう (謙譲の依頼形) | ① ~(し)ていただく ② お/ご~いただく ③ お/ご~願う | ① 待っていただく ② お待ちいただく ③ お待ち願う |
丁寧語
丁寧語の役割としては、言葉自体を丁寧にすることです。言葉にラッピングをして美しく演出します。
【丁寧語の基本パターン】
| 品詞 | 基本パターン | 具体例 |
|---|---|---|
| 名詞 | 前置き:「お/ご」 + 名詞 | お味噌汁、ご飯 |
| 文体 | ① ~だ/である。 (常体) ② ~です/ます。 (敬体) ③ ~ございます。(最敬体) | ① 私は〇〇だ/である。 ② 私は〇〇です。 ③ 私は〇〇でございます。 |
例外の特別表現
動詞の敬語については、次のような例外的な特別表現がありますので、マスターしましょう。
| 動詞 | 謙譲語 |
|---|---|
| 読む | 拝読する/いたす |
| 借りる | 拝借する/いたす |
| 聞く | 伺う、承る、拝聴する/いたす |
| 聞かせる | お耳に入れる |
| 見せる | お目にかける |
| 会う | お目にかかる |
| 動詞 | 尊敬語 | 謙譲語 |
|---|---|---|
| いる | いらっしゃる | おる |
| する | なさる | いたす |
| 言う | おっしゃる | 申す、申し上げる |
| 見る | ご覧になる | 拝見する/いたす |
| 行く | いらっしゃる | 参る、伺う |
| 来る | いらっしゃる、お越しになる、 おいでになる、おみえになる | 参る |
| 食べる | 召し上がる | いただく、頂戴する/いたす |
| もらう | 「受ける、受け取る」の基本パターン | いただく、頂戴する/いたす |
| 与える | くださる | 差しあげる、あげる |
| 知っている | 知って/ご存じでいらっしゃる | 知っておる、存じあげる |
普段から適切に敬語を用いる

ビジネスや日常生活を通して普段から正しい敬語を用いるようにすれば、二重敬語を使用する確率は自然と減っていきます。敬語は仕事や生活の中で使い慣れることが大切です。少し時間はかかりますが、慣れることにより、敬語を正しく使いこなせるようになります。
まとめ
二重敬語は、一つの言葉に対して同一の敬語を二重に重ねる言葉を意味します。連結敬語とは異なって、二重敬語は文法的に誤った表現と見なされるため、できるだけ使わないよう注意すべきです。
対策としては、二重敬語について知る、正しい敬語を理解する、仕事や日常生活において適切な敬語を使う機会を増やすように心がけましょう。